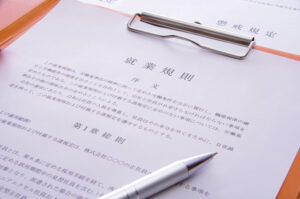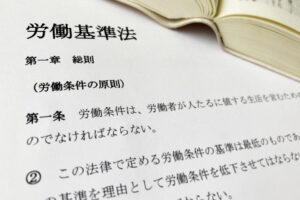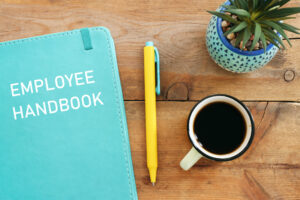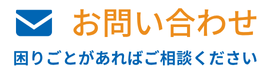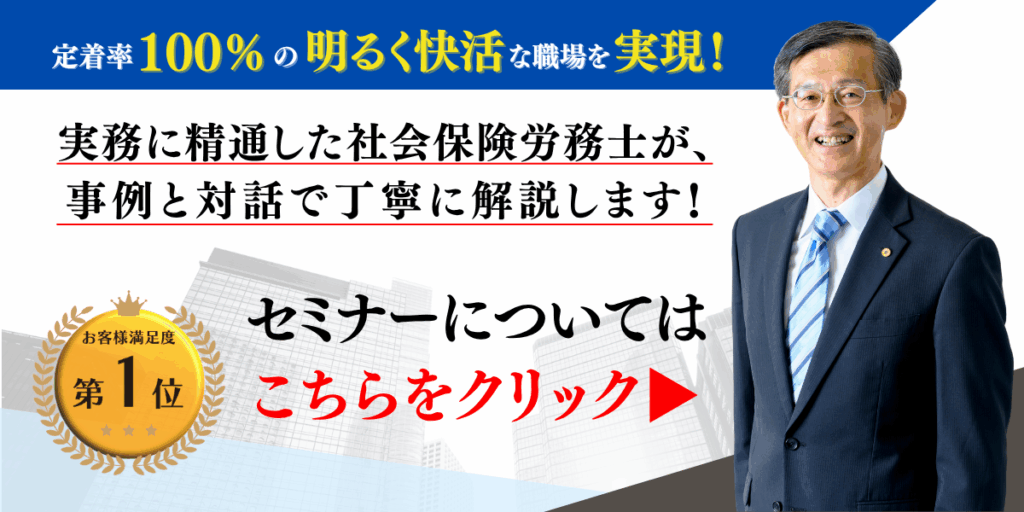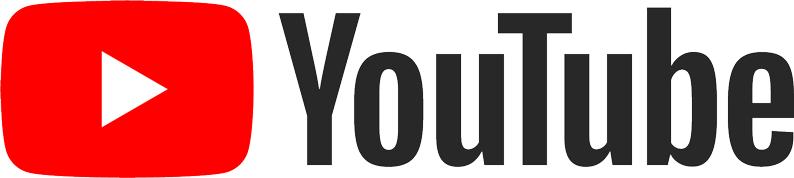就業規則の内容と労働基準法などの規定について
就業規則にはどのような内容を書けば良い?
「就業規則には何を書けば良いのか?」
これは多くの社長からいただくご相談です。
実は就業規則には、法律で必ず盛り込まなければならない内容と、自社のルールとして決めた場合に書かなければならない内容の二種類があります。例えば、
○必ず記載が必要な内容:労働時間、休日、賃金の決め方・支払方法、昇給、退職や解雇のルールなど
○会社で定める場合に必要な内容:退職金、臨時の手当、社員に負担させる費用、安全衛生、職業訓練、表彰・懲戒、災害補償など
これらを正しく整備しておかないと、トラブルが起きたときに「会社に不利」な扱いになってしまうこともあります。たとえば、法律に違反する内容を書いた場合、その部分は無効となり、強制的に法律どおりに修正されてしまいます。
つまり、就業規則は単なる形式ではなく、会社を守り、社員に安心して働いてもらうための“会社の憲法”なのです。
さらに、法律で決められた事項だけでなく、経営理念や会社の大切にしたい価値観を盛り込むことで、従業員の定着やモチベーション向上にもつながります。
労働基準法と労働契約法の規定

― 社長の経営を守り、社員が安心して働ける職場づくりを ―
就業規則は作って終わりではありません。社員への「周知」がされて初めて効力を持ちます。法律では、掲示・書面交付・データでの提供など、いずれかの方法で必ず従業員に伝えることが義務付けられています。これを怠ると、せっかく作った就業規則が“絵に描いた餅”になってしまいます。
さらに、就業規則を変更する際には大きな注意点があります。それは「不利益変更」です。たとえば労働時間や休日、賃金などを社員にとって不利に変更したい場合、法律上は原則として一人ひとりから合意を取らなければならないとされています。
「過半数代表の同意を取れば良いのでは?」と思われる社長も多いですが、実は違います。労働契約法では、個別に合意を得ないと裁判で負けてしまう可能性が高いのです。
「合理的な変更なら合意なしでも有効」とする例外規定もありますが、その判断を下すのは労働基準監督署ではなく裁判所です。つまり、裁判になって初めて有効かどうかが決まるため、経営上非常に大きなリスクを抱えることになります。
そのため、会社が不利益変更をしたい場合は、従業員説明会を開き、丁寧に説明し、一人ひとりから合意を得ておくことが安全です。特に「労働時間」「休日」「賃金」などの根幹部分については、個別合意を避けて変更するのは危険です。
専門家に任せて、リスクをゼロに近づける
就業規則の制定・改定は、法律知識と実務経験が不可欠です。誤った手順で進めてしまうと、後々のトラブルや裁判リスクに直結します。
御社の現状を丁寧にヒアリングし、経営者の想いを反映させながら、法律を遵守しつつ「社員が安心して働けるルール」としての就業規則づくりをお手伝いしています。
会社が弁護士などの専門家とも相談し、「合理的である」と考えた場合であっても、極力、個々の従業員から個別の合意を得ておくことが重要です。 一般的に、労働時間や休日の日数、賃金など労働条件のコアなところについて、不利益変更をする場合は、個別の合意を得ないで変更すると、ロクなことにならない(つまり、裁判で負ける。)と認識しておく方が無難です。
就業規則制定に関するご相談

おかど社会保険労務士事務所(代表・特定社会保険労務士 岡戸久敏)では、名古屋市、愛知県西三河・知多エリアを中心に、人事労務に関する業務を通じて、愛知のモノづくりの継続的な発展に貢献します。
就業規則の制定・作成でお困りの際は、
▼お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
就業規則の制定/改定・支援 各種メニュー