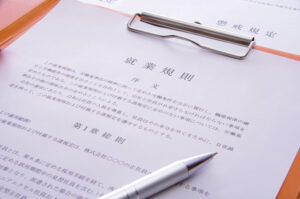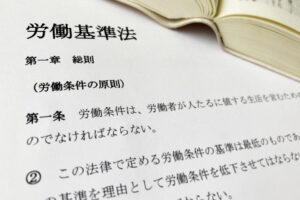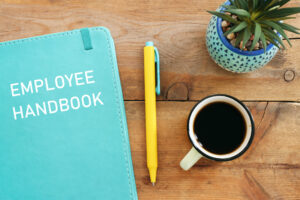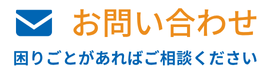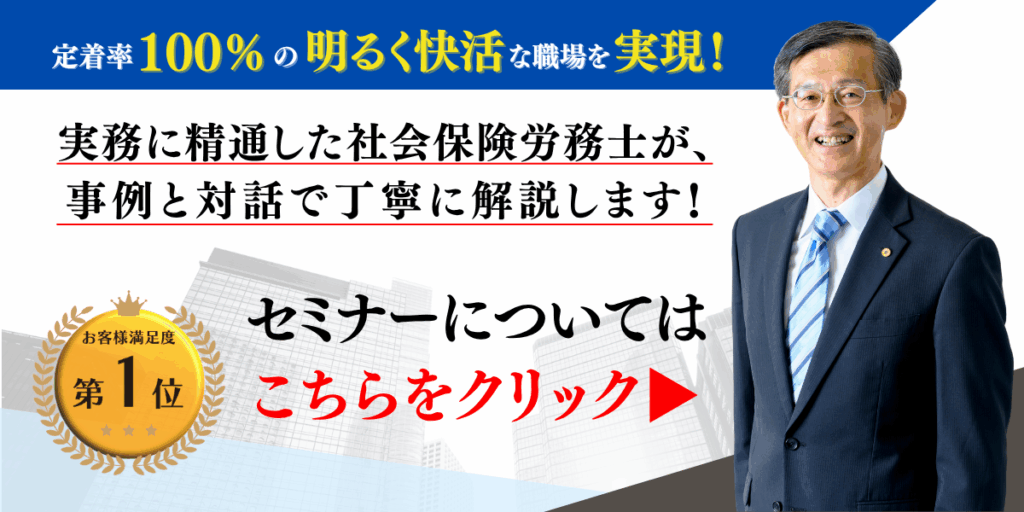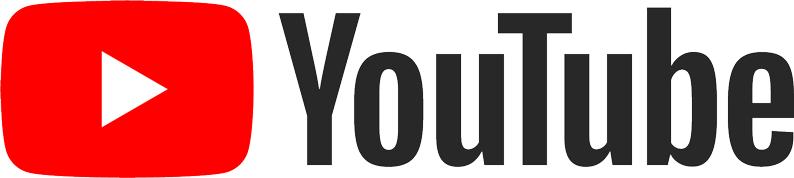就業規則の作成の流れと手順について
就業規則の作成の流れ
1 社内周知と従業員への意識づけ
「これから就業規則をつくる(改定する)」と社長から伝えることで、社員が当事者意識を持ち、協力体制が整います。
2 経営者の想いと現状のヒアリング
「どんな会社にしたいか」「いま何が課題か」をじっくり伺います。必要に応じて従業員へのアンケートや面談も行い、現場の声を拾い上げます。
3 現行規則の分析・工程表の提示
既存の規則がある場合は徹底的に分析し、改定の方向性とスケジュールを明確にします。
4 原案の作成とブラッシュアップ
法令に適合させるのはもちろん、その会社の理念や文化を反映させた規則案を作成。経営者と相談を重ね、必要に応じて従業員の意見も反映しながら完成度を高めます。
5 意見聴取・届け出・社内周知
労働基準監督署への届出を経て、全従業員に周知してはじめて有効になります。ここまでを責任を持って伴走します。
完成してからが本当のスタート
就業規則は「作って終わり」ではありません。
法改正や経営戦略の変化に合わせて、定期的な見直しが必要です。最新の状態を保ってこそ、会社と社員を守る力を発揮します。
就業規則の制定・改定に欠かせない「過半数代表」と届出サポート

就業規則を労働基準監督署に提出するには、ただ作って終わりではありません。
必ず「従業員代表」を選び、その代表者から意見をもらい、意見書を添えて届け出ることが法律で定められています。
ここで注意が必要なのは――
○管理職や経営者が勝手に代表者を決めることはできない
○パート・アルバイトも含めた全従業員の中から、投票や挙手で選ぶ必要がある
○就業規則は、労働者にきちんと周知して初めて効力を持つ
といった点です。
もしこの手続きを間違えてしまうと、「せっかく作った規則が無効」ということにもなりかねません。
私たちは、代表者の選び方から意見書の作成、労基署への届出、そして社員への周知まで、スムーズに進められるようトータルでサポートしています。
「法律的に正しく」「現場に合った」就業規則を整え、安心して経営に専念していただけるようお手伝いします。
就業規則制定に関するご相談

おかど社会保険労務士事務所(代表・特定社会保険労務士 岡戸久敏)では、名古屋市、愛知県西三河・知多エリアを中心に、人事労務に関する業務を通じて、愛知のモノづくりの継続的な発展に貢献します。
就業規則の制定・作成でお困りの際は、
▼お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
就業規則の制定/改定・支援 各種メニュー