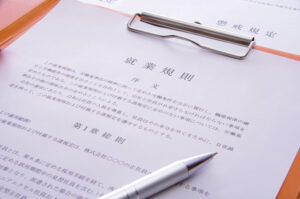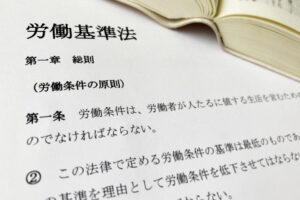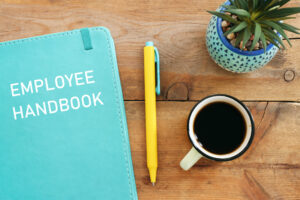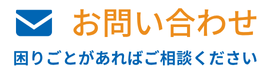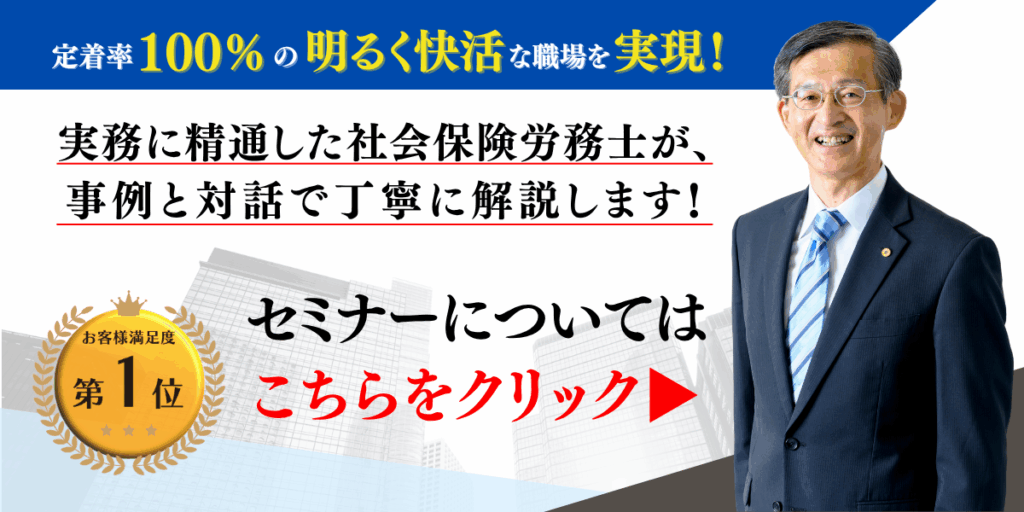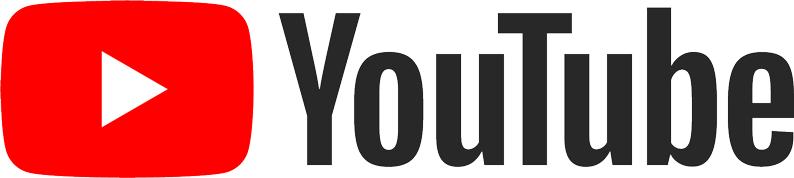就業規則の周知とは?社員説明の重要性
就業規則の周知とは何ですか?
就業規則の周知とは?
せっかく作った就業規則も、従業員に「周知」されていなければ効力を発揮しません。
つまり、就業規則はただ作って金庫にしまっておくだけでは意味がないのです。
法律(労働基準法第106条)では、会社は就業規則を次のいずれかの方法で従業員に周知しなければならないと定められています。
- 職場の見やすい場所に掲示、または備え付ける
- 従業員に書面を配布する
- データで保存し、職場で従業員がいつでも確認できるようにする
このいずれかを行って、はじめて就業規則は「効力を持つ」ものになります。
もし、上司の許可がないと見られない、経営者だけが金庫にしまい込んでいる――そんな状態では「周知した」とは言えず、法律違反となってしまいます。
なぜ大事か?
周知が徹底されていれば、従業員は「会社のルール」をいつでも確認でき、無用なトラブルを防げます。逆に、ルールが不透明だと社員の不信感や労務トラブルにつながり、経営者にとって大きなリスクになります。
社員説明の重要性を理解しよう!
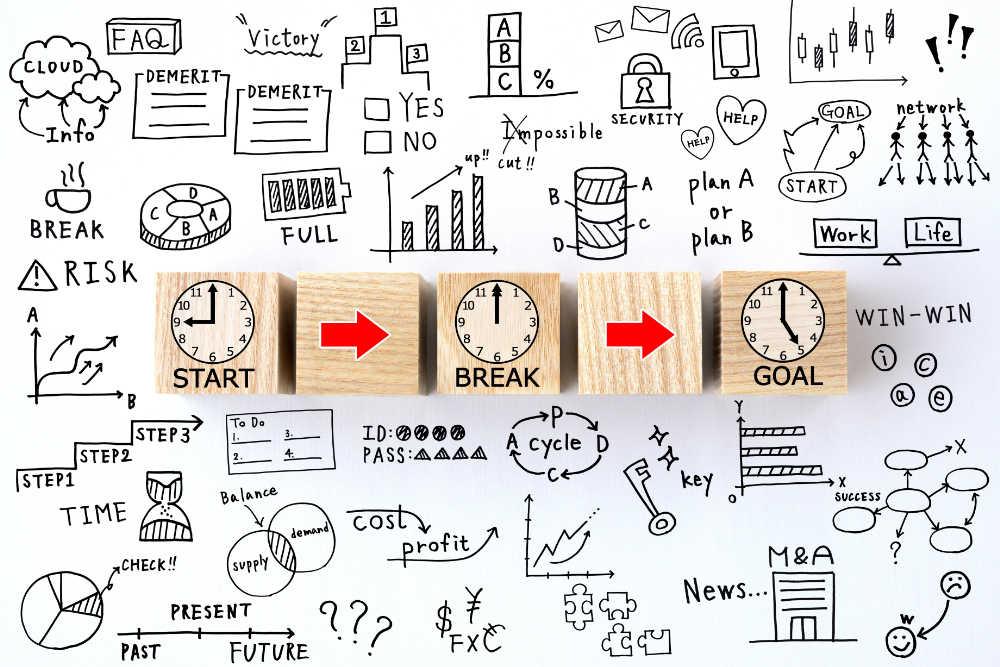
社員への説明は、会社を守り、社員を安心させる大切なステップです
法律上は、労働基準法で定められた方法で従業員に周知すれば「形式上」は問題ありません。
しかし実際には、人事担当以外の社員が就業規則を読み込み、正しく理解するのは難しいものです。理解不足のままでは、あとでトラブルにつながりかねません。
社労士による説明会のメリット
就業規則を作成した社労士が説明会を行えば、御社の状況に合わせた分かりやすい解説ができます。
従業員はすぐに理解でき、頭にも残りやすくなります。
例えば――
○有給休暇の申請方法
法律には「○日前までに申請」といった決まりはありません。電話やメールでの申請を認めるのか、緊急時はどうするのかは会社次第。社員が一番関心を持つ部分ですから、丁寧に説明することで混乱を防げます。
○ハラスメント対策
セクハラやパワハラに会社がどう対応するかを明確に説明しておくことで、被害者が泣き寝入りすることを防ぎ、抑止力にもつながります。上司にとっても「厳しい指導」と「パワハラ」の線引きが理解でき、安心して指導できます。
○改正法への対応
令和4年10月施行の「改正育児介護休業法」のように、複雑で理解しづらい法律も、専門家である社労士が噛み砕いて説明することで、社員の納得感を高められます。
社長にとってのメリット
○社員が就業規則を正しく理解することで、後々の労使トラブルを未然に防げる
○人事担当者の負担を軽減し、業務効率が上がる
○「社員に誠実な会社」という信頼を築ける
就業規則は「作って終わり」ではなく、社員に理解してもらってこそ力を発揮します。
説明会を実施することで、会社の方針が社員に浸透し、職場の安心感と一体感が高まります。
御社の就業規則の説明は、ぜひ私にお任せください。
社員が安心して働き、会社が堂々と前に進める環境づくりをお手伝いいたします。
就業規則制定に関するご相談

おかど社会保険労務士事務所(代表・特定社会保険労務士 岡戸久敏)では、名古屋市、愛知県西三河・知多エリアを中心に、人事労務に関する業務を通じて、愛知のモノづくりの継続的な発展に貢献します。
就業規則の制定・作成でお困りの際は、
▼お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
就業規則の制定/改定・支援 各種メニュー